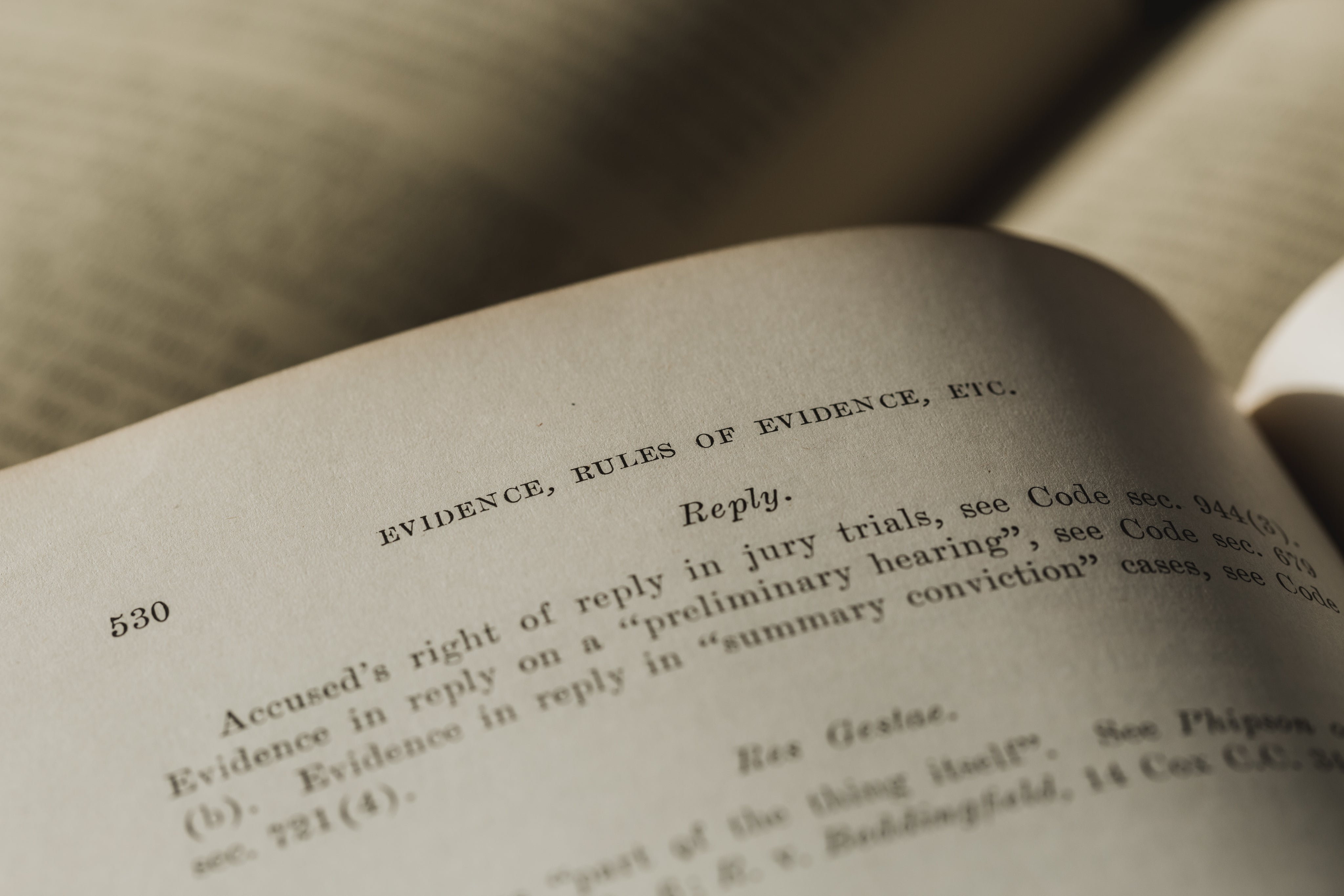タップ、タップ、タップ。
それは、ほんの寄り道のはず。
買い付けの旅の途中で、通過するだけのはずだった町
──イギリス・フージェール。
光と陰は、記憶を運ぶ。
この小さな町の教会の塔が空に向かって細く立ち、その影が町を優しく包み込んでいく頃、私は自分でも気づかぬうちに、立ち止まることの理由を求めていたのかもしれない。
午後の陽が傾きかけた頃だった。
町の教会の近く、川沿いの路地を歩いていると、一匹の猫くんと出会った。
サバトラ模様の中に、茶色がぽつりぽつりと混じる毛並み。ちらりと振り返って、まるで「もう!こっちへおいでよ。」と言わんばかりに尾をふわりと揺らして歩き出した。
どこかの家の子のようでもあり、町の主のようでもある。
でも私は、あの子を昔から知っていたような気がしていた。
だからかなんとなく、その子の後をついて歩いた。
なぜ猫に誘われると、人はついていきたくなるのだろう。その子は、私の中の声にも似ていた。迷いなく歩き、時折とまどい、振り返る。誰にも聞こえないけど、確かにあるような。
タップ、タップ、タップ。
彼の足音が、心の奥をノックする。
時々振り返って、「ちゃんと来てる?」と琥珀色の瞳が問いかけてくる。私は「いるよ。」と言葉で返事をして、不器用についていく。
やがて、視界がひらけた。
坂の上、町が一望できる小さな高台。噴水がある古い公園。その先には、金色と少しのローズがにじむ、静かな夕暮れが広がっていた。
空気の中を、角がおぼろげな光の粒がただよう。
彼の毛先が金色に縁どられ、屋根の灰青、煙突から立ちのぼる白、窓に映る夕日の欠片。そのすべてが、遠い記憶の断片みたいだった。
しばらく無言で眺めていると、その柔らかな光の中に溶けていってしまうようで。まるで「ひとり」と「孤独」の境界線が、光のなかに溶けてなくなるみたいだ。
出会いは、たいてい、外からやってくるように見えて、ほんとうは、自分の中でしか起こっていない。
ふと気づくと小さな彼は、ディープグリーンの生垣の小さな穴に、するりと姿を消していた。あの子はまた、誰かの心をそっとノックしに行くんだろう。